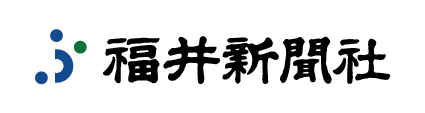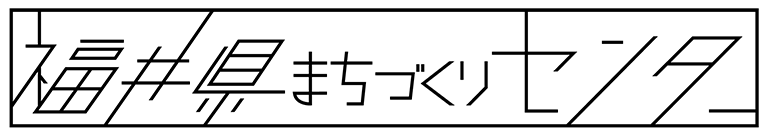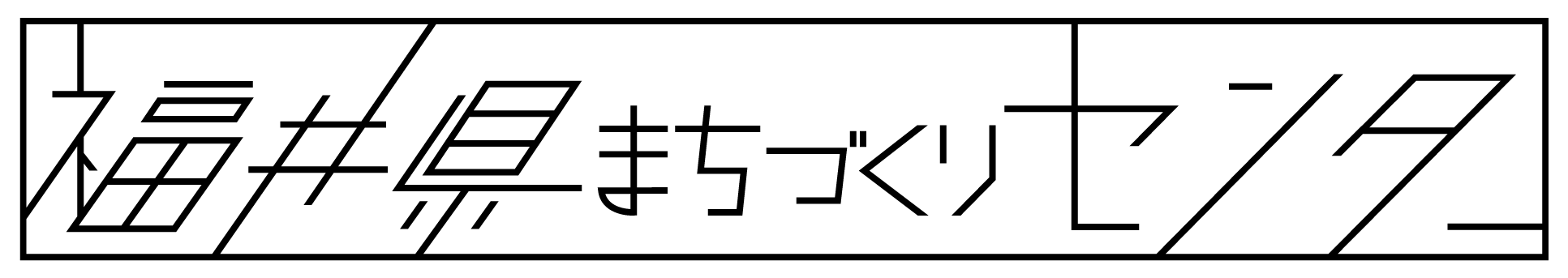| 設立 | 2020年4月 |
|---|---|
| 目的 | 地域課題の解決・より良い地域の創生の為 まちづくりプレイヤーの創出 |
| 理事 | 代表理事 竹本祐司(一般社団法人地域改革) 専務理事 高橋良彰(株式会社 福井新聞社) 理事 山田聡 (公益社団法人 福井青年会議所) 理事 和田敬信 (元福井県庁) 理事 岩井宏太(株式会社オールコネクト) 理事 堀一心(株式会社 fuプロダクション) |
| 事業内容 | ・プレイヤー育成事業 ・地域活性化事業 ・広報支援事業 ・プロジェクト事務局委託事業 ・共同販促事業 ・前各号に附帯関連する一切の事業 |
| 組織の特徴 | ・完全民営による自由度の高い組織でソフト構築 ・事業構築アドバイスとマネタイズサポートによるプレイヤー創出 ・行政、企業の情報を一元化して有益な調整を行う ・民間・行政の長所短所を生かし合い、福井活性化を目指す |
| 問い合わせ先 | 〒910-0006 福井県福井市中央1丁目9-24 福井中央ビル3階 TEL:0776-50-3578(平日9時~18時) MAIL:info@machidukuri.fukui.jp |
福井の課題解決・より良い福井を
「まちづくり」という言葉の定義は広いです。
弊社での定義は「自分だけでなく、福井全体がより良くなる活動」としております。
まちづくり活動を本業として行うことで、活動への覚悟と時間を増やし、質の高い活動を行い福井活性化に寄与したいと考えております。
弊社のパーパスは「意義のある仕事をしよう」とあるように、活動の目的から適切な施策を遂行し、福井活性化に繋がる意義のある仕事をする事を第一に掲げております。
意義の定義も広いですが、各担当者が自分の中の意義(信念)を持ち、活動する事を心がけております。
地域活性化のソリューションを生み出し、全国に届け、地域活性化に貢献する
グループ会社に日本の地域活性化を行っている「一般社団法人地域改革」があります。
一般社団法人福井県まちづくりセンターで生み出した、様々なソリューションを日本全国に届け、地域活性化に貢献をします。
福井で経験を積んだスタッフが、将来県外で活躍していきます。
地域活性化はプレイヤー次第
同じコンテンツでも「人」次第で成功(正解)にも失敗(不正解)にもなり得ます。
例えば、数ある出会いのイベントは 同じコンテンツでも成功もあれば失敗もあります。
コンテンツに罪はなく、行う人次第です。
各々、推したいコンテンツや思いはあるが成功させた人のやりたい事が正解になります。
やらない人がやる事を決めても、誰もやらない
やる人がやる事を決めるから可能性が生まれる
言っても、待っても、誰もしてくれないし、何も始まらないです。
自分が思う事を正解にしたいなら自分がやるしかないです。
これからを「正解」にするのは「人」次第人=「プレイヤー」と考えます。
まちづくり活動が継続しにくい理由
まちづくり活動の多くは縮小・衰退します。理由は、対価が合わない事にあります。
まちづくり活動の殆どが地域に貢献したいという「感情対価」で始めますが、活動を続けるうちに同じ対価を得るには活動量を増やさないといけない傾向にあり、対価が合わず活動疲れとなります。 感情対価で不足する部分を「報酬対価」を得る事を推奨しております。 まちづくり活動は稼げないという人がいますが、逆に強みを活かせば稼ぎやすいです。 そのノウハウを展開し福井活性化に寄与します。
優良なソフト事業が生まれない土壌
優良なソフト事業とは、<①熱い思い>から始まり、<②スピード感と尖ったコンテンツ>を有し、<③多くの失敗と成功の繰り返しによるノウハウの蓄積>の繰り返しにより生まれると考えます。ソフト事業は行政が行うべきという考えもあるかもしれませんが弊社では民間が主導で行うべきだと考えます。
行政の組織上、担当者が変わってしまうために①と③が引き継げず、合意形成により②も難しい場合が多いです。また、「やる人がやる事を決める」のではなく、「やらない人がやる事を決める」ことも課題の1つです。
「人」に投資を
これまでのソフト事業の多くは、一過性が多く、例えば補助金を充てた場合も無くなれば終了する事が多いです。持続可能な事業にするためには「人」に投資をすることが必要です。「事業」だけに投資を使えば投資を行い続けなくては継続ができません。「事業」をつくる「人」に投資を行えば成長し資産化されます。投資を使い捨てではなく、資産になるような人材育成に充てていくことが重要だと考えます。
ビジネス要素が足りない
まちづくりに圧倒的に足りないものはビジネス⇒稼ぐ力。
稼ぐためにまちづくりを行っているわけではないですが、行っている事業が素晴らしいのであれば継続する為に稼いで頂きたい。
情熱で始まり情熱で終わるプロジェクトを多く見てきました。9割以上だと思っております。
情熱で始まりメリットで継続する。対価を求め、対価を与えましょう。
コンテンツをプロとして提供し、プライドを持ち価値を提供しましょう。
ビジネス化できている時、そのプロジェクトは大きな価値を提供できていると思います。



関連会社
supported by